
橋梁の設計案件は、新しく橋を架ける新設と既存橋梁の補修に大別されます。
新設の場合は上流側の業務である調査・計画の段階から携わり、基本設計を経て実施設計を仕上げ、設計図書をお客様に納品するまでの全工程に関わります。お客様は官公庁が大半で、各種申請手続きなどの事務業務もあります。
私は入社2年目に初めて新設橋梁の設計を担当し、現在は2つめの新設橋梁の仕事がスタートしたところです。補修案件の場合は、設計だけでなく既存橋梁の点検・診断も行います。
その点検・診断の単独案件もあり、私も入社1年目から現在まで何度か経験しました。たとえば点検ハンマーなどの器具を用いてコンクリート剥落の予兆を見極めたり、ひび割れのレベルを調べるなど、業務内容はかなり奥が深そうです。
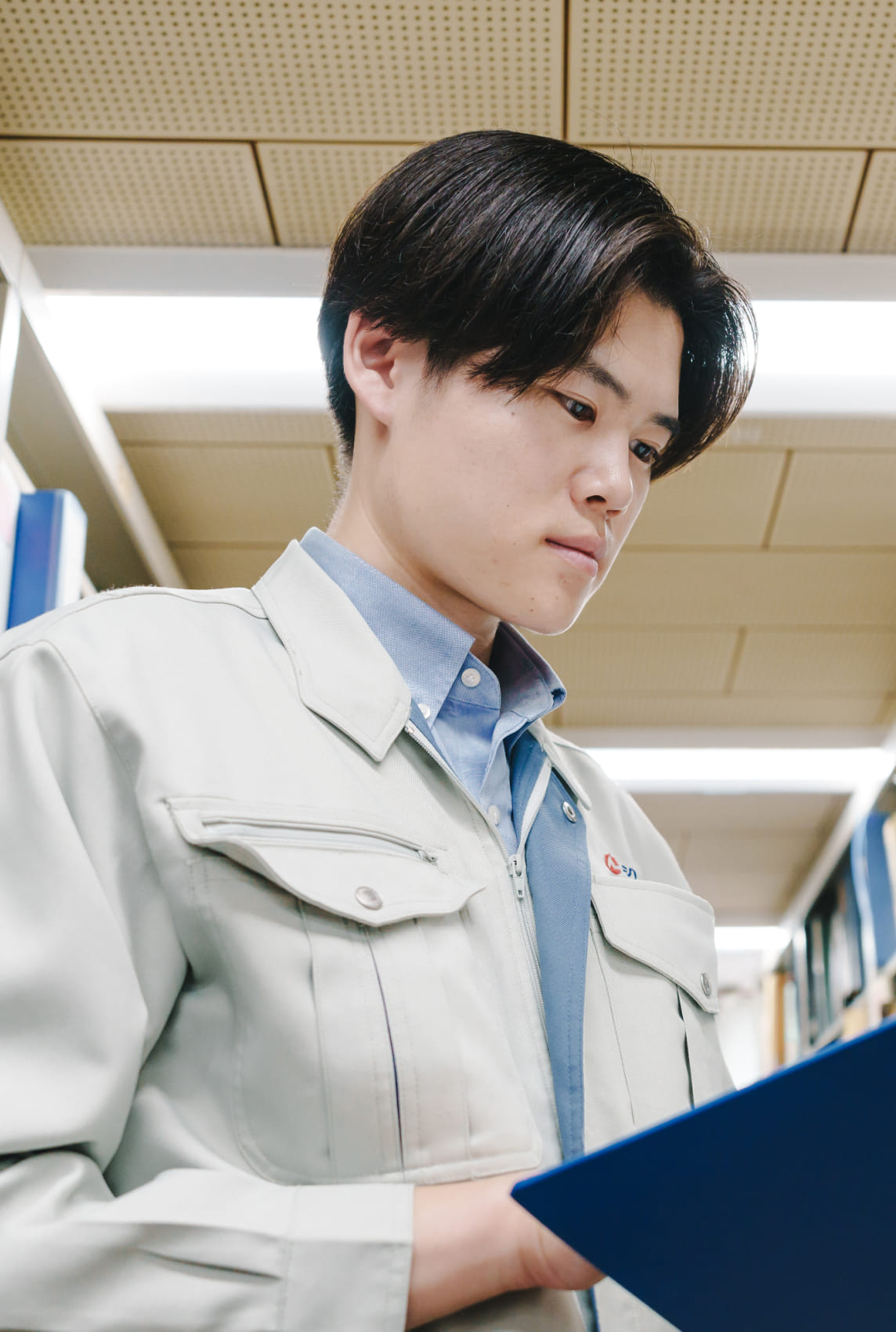

現在、入社3年目で2件目の橋梁の新設(架け替え)設計を担当しています。1件目の時は知識や経験がゼロからのスタートだったので、実践→報告→修正、つまり調べたり考えたり上司に教わったりを限りなく繰り返して、最後までやり遂げました。
この経験があるから次は大丈夫…と思ったら、今回は規模からして1件目のほぼ倍、工事内容や工法に関しても初めてのテーマが多く、やっぱりイチから勉強の繰り返しです。大変っちゃ大変だけど、だからこそ面白い。橋梁案件はすべてオーダーメイド。未知の条件や技術課題に毎回必ず直面するから、常に新鮮な気持ちで臨めます。
あと、いつもお世話になっている先輩の指導法が絶妙で、助かっています。進行中の橋梁案件でも、部内で前例のない撤去計画の立案に際し、「別件事例だけどこういうのがあったよ」と、さりげなくヒントを。考える意欲を引き出してくれる環境で、成長を日々実感しています。
入社以来、計画から実施設計まで全工程に関われた仕事は、実質的にまだ1件。それだけに印象深く、忘れられない仕事になりました。
案件は、宇和島市の山間部を流れる二級河川に架かる長さ10mほどの橋梁です。近年頻発する豪雨の影響で既存の橋梁の橋桁と河床の間に土砂や流木が詰まってしまい、河川が氾濫したため架け替えが決まったという経緯があります。計画段階から現地を何度も訪れ、既存の橋を壊して新設工事を進める間の仮橋の形状や強度、橋桁上の柵はガードレールで…など、さまざまな角度から検討を重ね、設計図書の納品まで1年がかりで完走。私にとっては自分の中の引き出しゼロからスタートし、先輩や上司に助けていただきながら、無我夢中で駆け抜けた1年でした。
現在は、既存の橋の取り壊しの前に仮橋の工事が進んでいる段階だと思います。現地までは車で3時間ほど。竣工・供用後はもちろん、現地に行って仕上がりを自分の目で確認するつもりです。

一人前になるには10年、20年かかる。それが土木設計の世界…といったお話を社内の大先輩に聞いたことがあります。土木構造物は少なくとも数十年にわたって社会を支えるインフラなので、それも当然。入社3年目の私にできることは、まだまだ土木設計、いえ橋梁設計のごく一部分にすぎない。そのことを自覚し、目の前の仕事でしっかり結果を出しながら経験値を高めていけたら、と思っています。
当面は、上司や先輩の助けがなくても、全工程を自分の力でやり遂げられる実力を磨きたいですね。何年かかるか… あまり焦らず急がず、長い目でじっくり取り組んでいきたいと考えています。

午前中は、現在担当している橋の架け替えに関して、既存橋梁の撤去方法を検討。工程は?日数は?など、検討内容が多岐にわたるので、じっくり時間をかける。
橋梁工事の現地調査に車で出かける。
前回の視察では、撤去に備えて現役橋梁の構造物の厚みや材質などを細かくチェック。
この日は最大通過重量、つまりセミトレーラーやダンプトラックといった工事車両が何トン車まで橋を通れるかなど、施工に関わるさまざまな条件を調査・確認。
調査内容の精査・整理。上司への報告はある程度まとまった段階で行う。
先輩方のサポートに入り、進行中の担当案件に関する計算書や図面をチェック。
自分の勉強にもなるので、進んでヘルプに入るようにしている。
残業は平均30時間/月ないくらい。定時で帰る日も多い。
週末に有休をプラスして旅行に出かけることが多いですね。四国内に加えて淡路島など、けっこう頻繁に行きます。東京ディズニーシーに行ったときは有休を2日取りました。余談ですけど、有休の取りやすさはシアテックの大きな魅力のひとつ。入社初年度に有休を20日もらえる会社はたぶん珍しいと思います。ちなみに私はそのうち18日を消化。たぶん社内では普通です。
旅行以外の土曜日は、バスケ部の練習に参加。土木部の先輩に誘われて入部しました。バスケ経験はないのですが、いつかやってみたいと思っていたので、ちょうどよかったですね。他にもサッカーやバドミントン、テニスなど、いろいろな活動があるようです。
